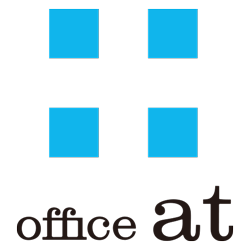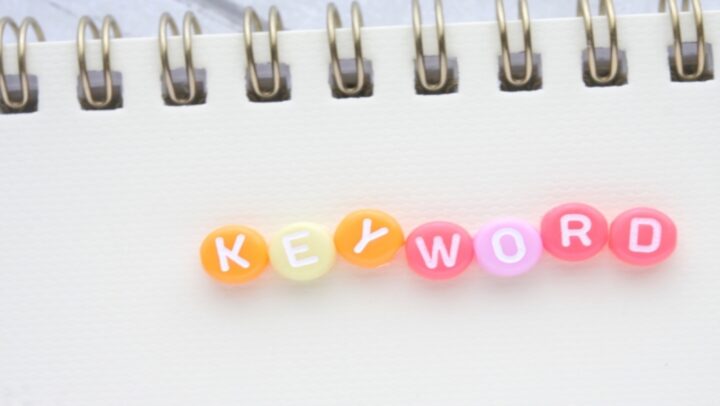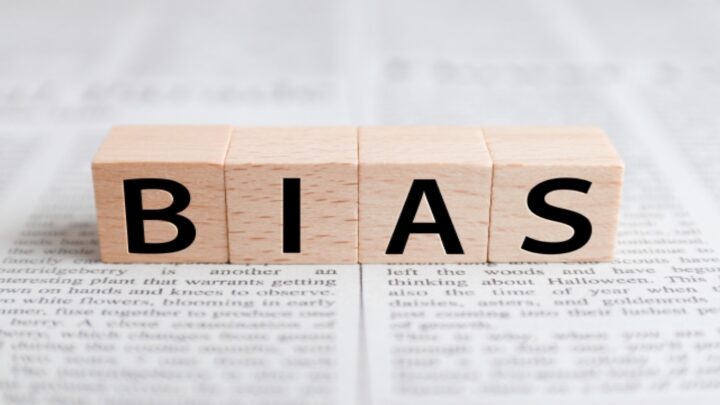日本の出生率が過去最低更新 もう待ってられない!私たちができることは?
先週、昨年の合計特殊出生率が1.2と、
過去最低を更新したというニュースが
駆け巡りました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240606/k10014472291000.html
人口が先細りということは、
人手不足はますますひどくなり、
私たちの生活に密着する行政サービスなどの
縮小も進むと考えられ、どんよりしてきますね。
ただ女性としては「産むかどうかは個人の勝手」ですし、
「産めよ増やせよ」なんて国に介入されたくない
それが正直なところだと思います。
次々とプランニングされる「少子化対策」も
意識を変えさせようとお金を積んで
個人に背負わせるのではなく、
社会全体の課題をひとつずつ解決していかないと
効果はないんじゃないかと思います。
ということで、課題はどんな所にあるのか、
少しでも私たちに何かできることはないのか、
ちょっぴり深掘りしてみたいと思います。
人口を維持するには、
出生率が2.07以上必要なんだそうです。
日本は1974年に2.07を下回って以来低下傾向を続け、
総人口は2008年をピークに減り続けています。
そして各県のランキングはこんな感じです。
https://www.nhk.or.jp/shutoken/articles/101/005/79/files/0605_shusshou.jpg
全体的にランキング上位には九州など
西日本エリアや北陸の県が並んでいます。
最下位の東京はついに1を割り込みました。
やっぱり東京の女性は子育てせずバリバリ仕事をし、
地方は実家も近いし子育てしやすいんだなぁ
と思いましたか?
まあその解釈もあるとは思いますが、
少し別の面も見えてきます。
まず東京の数値が低いのは、
家庭を持つと東京から出て行くからではないかと。
全国から20代の若者が集まる東京ですが、
結婚して出産するとなると、
都内から自然豊かな郊外に出て行きますよね。
また、地方についてはこんな解釈もあります。
「地方の合計特殊出生率の高さは、
ローカリズムが支持された結果ではなく、
リベラルで多様な価値観を持つ女性たちが都会に逃げていき、
保守的な女性だけが地方に残った結果として
達成されているのではないだろうか。」
※「女子」に選ばれる地方(十六総合研究所提言書)より
https://www.amazon.co.jp/「女子」に選ばれる地方-十六総合研究所-提言書-2022-十六総合研究所編集委員会/dp/4877973109
親戚の集まり、組合の集まり、、、
地方では古い慣習がなかなか変わらないので
逃げていく女子たちの気持ちもわかります。
そして都会へ出た男性はUターンも多いのですが、
女性はほとんど戻って来ないというデータも。
皆さんはどう思われますか?
それから出生率上位の九州や北陸の県は
こちらのランキングと似通っていませんか。
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/4120/
つまり、専業主婦が多い都会よりも
共働きが多い県の方が出生率が高いのです。
これは経済力と関係があると言えます。
また晩婚化、晩産化も問題です。
動物としての人間の出産適齢期は25歳~34歳で、
35歳過ぎると妊娠率が一気にダウンし、
40歳になるとほぼ自然妊娠はできなくなります。
実はそのことを女性たちはほぼ学んでいません。
入社して、子育てはキャリアを積んでから、
などと考えているとあっという間に35歳に。
不妊に悩む夫婦の割合は、今や5組に1組もいて
私が結婚した30年前の10組に1組から倍増しています。
なぜそうなるかというと、
女性の大卒が増えて入社年齢が上がっていることと、
男女平等の働き方と評価制度がそうなっているから。
男性と同じように働いていて評価されたい
そう考えて出産を先延ばしにしてしまうことを
責めることはできません。
これを解決するために対策している企業もあります。
キリンでは「早回しキャリア形成」といって、
女性たちが出産・育児前の若いうちに
プロジェクトリーダーなど責任ある経験を積ませ
自信を持たせたうえで、主体的にライフイベントや
休業期間を選択してもらおうとしています。
男性も変わる必要があります。
子育ては女性だけがするものではありません。
男女平等の文脈でよく言われるのが
「男女一緒に100m走のスタートラインに立ったら
女性だけ障害物競走だった」というもの。
これでは産み育てるのに躊躇するのは必至です。
男性の育児や家事参加はもっと増えるべきですし
そうしたいと考える若い男性は増えています。
なのにできないのは、長時間労働など
上司や企業の問題です。
男性の育児休業は年々増えてはいますが、
国のいう「2025年には30%」には程遠い数字です。
子どもを授かった男性に「育休はどうする?」と
必ず聞かないといけない法律があること
ご存じでしたか?
私の周囲ではいまだに
「お前1ヵ月も休んだら帰ってきても椅子はないぞ」
などと脅す上司の話を聞きますから愕然とします。
男性側が休まないのは金銭面の心配もあります。
が、ダブルで働いている今の夫婦にとっては、
どちらが休んでも同じことです。
ちなみに日本の育休制度は世界一恵まれています。
それらの内容を社員に認知させることも必要です。
男性の育休取得率が3%から2年で91%になった
株式会社タカギ(北九州市)のような事例もあります。
通常の有休とは別に20日間の有休が付与されることと、
人事評価に影響しないという認識が広がったことが
最大の要因だそう。
以前インタビューした動画です
↓
https://www.youtube.com/watch?v=sXkthYoEKIE
未婚率も増えていますがこれも、
男性の家事育児進出が足りないことと繋がっています。
Z世代の女性たちが結婚相手に求めるものは、
1位は「やさしさ」ですが、2位は「家事力」です。
私の時代は「高収入・高学歴・高身長」の3高でしたが
今の女子たちは相手に「経済力」を求めません。
なぜなら自分で稼げるからです。
それより大切なのは私をサポートしてくれる
パートナーの「家事力」なんですね。
未婚率を減らすためにも、
会社にだけ縛り付けていてはいけません。
さて、世界に目を向けると、、、、
長くなったので今回はこの辺でやめておきます。

☆求人広告・採用ブランディング・講座・社外メンターほか
ご相談はお気軽にどうぞ!